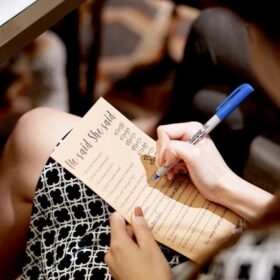「同窓会」と聞くと、懐かしい顔ぶれとの再会にワクワクする一方で、司会という大役を任されたあなたは少し緊張しているかもしれませんね。
でも大丈夫。司会は「参加者を楽しませるエンターテイナー」であると同時に、「会をスムーズに進める進行役」です。
成功の鍵は、完璧な進行を目指すのではなく、温かく、おおらかな雰囲気を作ることにあります。
大切なのは、参加者全員が「来てよかった!」と感じられるような空間を作り出すこと。そのためには、まずあなたがリラックスして、会そのものを楽しむ姿勢が一番重要です。
そして、事前の準備をしっかり行うことで、当日も自信を持って臨めます。
司会はプロでなくても大丈夫。ちょっとしたコツや事前準備で、誰でも参加者全員が楽しめる、最高の同窓会を演出することができます。この記事では、開会から閉会まで、スムーズに、そして最大限に同窓会を盛り上げるための司会進行のポイントを、具体的な台本例も交えて徹底解説します。
同窓会を成功させるために気を付けるポイント

1. 大きな声で話す
司会進行役にとって最も大切なのは、大きな声で話すことです。同窓会のようなカジュアルな場では、流暢な話し方よりも、勢いのある明るい声の方が好印象を与えます。
声が小さいと自信がないように聞こえ、参加者を不安にさせてしまう可能性もあります。普段から大きな声を出す習慣がない方は、本番前に腹式呼吸を意識して練習してみましょう。「お腹から声を出す」ことを意識するだけで、声量が増し、堂々とした印象を与えることができます。
2. 台本を見すぎない
司会が台本を見ることは決して悪いことではありません。しかし、台本を常に見ながら話してしまうと、気持ちがこもっていないように感じられてしまいます。また、顔が下を向くことで声がこもり、聞き取りにくくなることも。
台本を丸暗記する必要はありませんが、次の流れを常に頭に入れておきましょう。本番前に数回練習するだけでも、心の余裕は大きく変わります。参加者一人ひとりの顔を見て、アイコンタクトを取りながら話すことで、より親近感のある司会進行ができます。
3. 喋りすぎない
司会進行役はあくまで「進行役」です。自分の話に夢中になりすぎて、時間を押したり、参加者の話す機会を奪ったりしないように注意しましょう。特に、普段から話が長いと言われる方は意識が必要です。
ついテンションが上がって喋りすぎてしまうのが心配な場合は、台本にセリフごとの分数や秒数を書き込んでおくのがおすすめです。時間の目安を意識することで、進行役という本来の役割に集中できます。
同窓会での司会進行の流れ

司会進行台本を作成する前に、まずは同窓会の一般的な流れを把握しておきましょう。全体の流れを理解することで、タイムスケジュールに合わせた効果的な台本が作れます。
同窓会は、会場の使用時間にもよりますが、一般的に2〜3時間で組まれることが多いです。以下に、よくあるプログラム例をご紹介しますので、台本作成の参考にしてください。
1. 開会の挨拶
同窓会の始まりを告げる大切な挨拶です。明るく元気な声で、会の雰囲気を盛り上げましょう。
「皆様、本日はお忙しい中、ご来場いただき誠にありがとうございます。これより、〇〇中学校 第〇期卒業生の同窓会を開会いたします。
わたくし、本日司会を担当させていただきます、元3年〇組の□□太郎です。どうぞよろしくお願いいたします。本日は限られた時間ですが、学生時代に戻ったつもりで、思い出話に花を咲かせましょう!」
■先生が出席している場合
「また、本日は、〇〇先生、〇〇先生にもご臨席いただいております。(先生の方を向いて名前を呼ぶ)先生方、本日はご来会いただき、誠にありがとうございます。短い時間ではありますが、先生方を交えて、全員で学生時代に戻った懐かしいひとときを過ごしましょう。」
開会の挨拶では、司会者自身が元気な声で、楽しんでいる姿勢を見せることが大切です。場合によっては、開会の挨拶の後に別の幹事が代表挨拶をすることもありますが、いずれにしても、明るく元気な雰囲気を作ることを心がけましょう。
2. 恩師紹介
恩師の先生方への敬意を表し、紹介の時間を設けましょう。先生の紹介に加えて、担当していたクラスや部活動などの情報を添えることで、参加者の学生時代の記憶がより鮮明に蘇ります。
「さて、ここで、本日ご臨席いただきました先生方をご紹介します。ご紹介の後、先生方には一言ずつご挨拶を頂戴したいと思います。先生方、どうぞよろしくお願いいたします。
最初にご挨拶いただくのは、テニス部の顧問で元3年1組の担任をされていた、〇〇先生です。〇〇先生、どうぞ前へお進みください。」
先生には順番に登壇してもらい、その都度紹介しましょう。
「〇〇先生、〇〇先生」のように、お名前をはっきりと言いましょう。
先生が担当していたクラスや部活動、教科などの情報を付け加えると、参加者の心に響きます。
3. 乾杯の挨拶

乾杯の挨拶は、同窓会をスタートさせる重要な儀式です。事前に適任者を選んで依頼しておきましょう。司会は、あくまで進行役に徹し、挨拶をする人にスポットライトを当てることが大切です。
「続きまして、これより乾杯に移りたいと思います。皆様、お手元にグラスのご準備をお願いいたします。ご準備はよろしいでしょうか?
それでは、乾杯の挨拶を、〇〇先生(または〇〇さん)にお願いいたします。〇〇先生(〇〇さん)、どうぞステージ前の中央へお越しいただけますでしょうか。」
(※乾杯の挨拶後)
「〇〇先生(〇〇さん)、ありがとうございました。それでは皆さん、再会を祝して、乾杯!」
乾杯の挨拶は、司会のセリフを最小限に抑え、挨拶をする人の紹介と、乾杯後のお礼に徹しましょう。
先生からお心づけ(ご芳志)をいただいた場合は、この乾杯の挨拶の前に紹介し、感謝の気持ちを伝えるのが一般的です。
4. 食事・歓談
乾杯が終わったら、すぐに食事と歓談の時間を始めましょう。参加者はお腹を空かせているかもしれませんし、久しぶりの再会で早く話したいと思っているはずです。
「それでは、お料理も揃っておりますので、しばしお食事とご歓談をお楽しみください!」
5. 余興・ゲーム

参加者を楽しませる余興やゲームのコーナーです。食事・歓談の時間の終盤に、一度会場を落ち着かせてから、プログラムについてアナウンスします。ここからは、さらに明るく楽しい雰囲気で会場を盛り上げていきましょう。
余興の場合
「皆様、お食事、ご歓談はお楽しみいただけましたでしょうか?それでは、ここからはスペシャルパフォーマンスの時間です!
〇〇さんによるスペシャルパフォーマンスをご披露いただきます!ぜひ、ステージにご注目ください。それでは、パフォーマーの皆様、よろしくお願いいたします!」
■余興後
「素晴らしいパフォーマンスを披露してくださった皆様、ありがとうございました!とても〇〇で(簡潔な感想)、感動いたしました。皆様、もう一度盛大な拍手をお願いいたします!」
(拍手が落ち着いたら)
「それでは、今しばらくお食事とご歓談をお楽しみください。」
ゲームの場合
「皆様、大変お待たせいたしました!それでは、これより〇〇ゲームを始めたいと思います!
優勝チームには豪華賞品をご用意していますので、張り切ってご参加ください!それではまず、ゲームのルールについてご説明します。」
■ゲーム後
「優勝チームの皆様、本当におめでとうございます!そして、ご参加いただいた皆様、ありがとうございました!
皆様の**〇〇な姿(例:真剣な姿、楽しそうな笑顔など)**は、学生時代に負けないくらい輝いていました。大いに楽しませていただきました。
まだまだお料理もございますので、引き続き、お席でおくつろぎください。
余興やゲームの後には、出演者や参加者への感謝の気持ちを伝えることが大切です。
感想を簡潔に述べることで、会場の一体感をさらに高められます。
その後、再び食事と歓談の時間を促し、参加者が自由に交流できる時間を作りましょう。
6. 校歌斉唱
同窓会のクライマックスを盛り上げる校歌斉唱。参加者全員で歌うことで、一体感が生まれます。
「皆様、これより全員で校歌斉唱をしたいと思います。受付でお配りしましたプリントをお手元にご用意ください。それでは〇〇さん(音響スタッフ)、よろしくお願いいたします。」
参加者がプリントを準備する時間を確保しましょう。
音響スタッフと事前に打ち合わせをして、スムーズに音楽が流れるようにしておきましょう。
7. 記念撮影
大切な思い出を形に残す記念撮影。スムーズな進行を心がけ、参加者全員がカメラに収まるように誘導しましょう。
「それでは、これより記念撮影を行いたいと思います。まず先にクラスごと、最後に学年全体での撮影とさせていただきます。
こちらから順次クラスごとにお声がけしますので、該当する方はゆっくりとステージにお上がりください。〇〇さん(幹事)、撮影される皆様のご誘導をお願いします。撮影担当の〇〇さん、よろしくお願いいたします。」
撮影の流れを簡潔に、分かりやすくアナウンスしましょう。
幹事や撮影担当と事前に連携を取り、スムーズな誘導を心がけましょう。
8. 締めの挨拶

同窓会の締めくくりとして、一本締めや一丁締めを行います。
「皆様、宴もたけなわではございますが、そろそろお時間がきたようですので、締めに移りたいと思います。締めの挨拶は幹事を代表して〇〇さんにお願いします。〇〇さん、よろしくお願いいたします。」
(※締めの挨拶後)
「それでは、ここにお集まりの皆様の益々のご活躍とご健康を祈って、一本締め(または一丁締め)で締めたいと思います。皆様、ご準備はよろしいでしょうか?
それでは、お手を拝借。よぉーっ! パン!(一丁締め) または パパパン、パパパン、パパパン、パン!(一本締め)」
事前に、一本締めか一丁締めかを決めておきましょう。
手拍子のタイミングを参加者に伝えることで、一体感が生まれます。
9. 閉会の挨拶
参加者への感謝を述べ、同窓会を締めくくります。司会者が締めの挨拶から続けて行ってもかまいません。
「本日はこのように、多くの同窓生、そして〇〇先生、〇〇先生とも再会でき、楽しいひとときを過ごせました。次回の同窓会がいつになるかは分かりませんが、再びお会いするときに先生に間違われないよう、健康に気をつけて若さを維持したいと思います!
皆様、本日はお忙しい中ご来会いただき、誠にありがとうございました。」
参加者への感謝の気持ちを伝えることが最も大切です。
同窓会を振り返り、親しみを込めた言葉で締めくくりましょう。
まとめ

同窓会の司会は、ただ会を進行するだけでなく、参加者全員が心から「来てよかった!」と思えるような温かい雰囲気を作り出す大切な役割です。
この記事でご紹介した台本例とポイントを参考に、しっかりと準備をすれば、あなたも間違いなく「名司会」として称賛されるでしょう。大きな声で明るく、そして何よりもあなた自身が同窓会を楽しむことが成功の鍵です。
昔の仲間との再会を心ゆくまで楽しみながら、最高の思い出に残る一日を演出してください。
関連記事

東京都内の同窓会はサンシャインクルーズ・クルーズがオススメ

1.店内13の個室会場完備だから人数規模に合わせて同窓会の開催可能
池袋・サンシャイン60ビル・58階にあるサンシャインクルーズ・クルーズは、大小合わせて13の会場があり、人数に合わせて会場希望を変更できるのが特徴です。
周年の同窓会のように大規模なパーティーが、地上210mの絶景と共に参加者皆様にお楽しみいただけます。
パーティープランナーがそれぞれのお客様に合った会場をご提案いたしますので、規模を問わず気軽に相談いただけます。
2. 駅近で、さらに首都高速やエアポートリムジンなど、アクセスが充実
全国的にも有名な商業施設であるサンシャインシティ内に位置し、各種交通機関でのアクセスが簡単なので、地方から参加される方も安心です。
巨大なターミナル駅である池袋駅からのご案内動画もあるので、幹事様のルート案内の負担が軽減されます。
サンシャインシティ内にあるサンシャインシティプリンスホテルとも宿泊提携サービスもあり遠方からの参加者にも安心です。
3. ホテルの宴会場レベルの充実設備と豊富なオプションをご用意
着席最大350名、立食最大500名まで収容可能な地上210mの大会場は、スクリーン・プロジェクターが5台、ワイヤレスマイク4本、ミキサーやスイッチャー、照明切替装置など、様々な設備をご用意しています。
今までホテルで開催してきた同窓会を当店に変更いただいても、スムーズな開催が可能です。
ステージ上を撮影し、会場内に映像配信できるカメラは特に人気の設備です。設備のほとんどは会場費の中に使用料金が含まれるので料金面も安心です。
4. 同窓会が楽しくなる機能満載のデジタルツールが無料でご利用可能
同窓会の開催では、「同窓会への招待」と「参加者の管理」が幹事様にとって一番大変な作業と言われています。
その課題を簡単に解決し、さらに同窓会での思い出作りに最適な機能が豊富なデジタルツール
【Biluce(ビルーチェ)】が、サンシャインクルーズ・クルーズをご利用いただくことで、有料プラン機能も含めて無料でご利用いただけます。
※80名様以上の同窓会ご予約のお客様が対象です
5. 年間費・入会金無料のポイントカードはご利用代金の5%を還元
当社系列全店でポイントを共有して「貯める」「使用する」が可能な【クラブクルーズポイント会員】は、入会金・年間費無料で、パーティーのポイントを貯めることが可能です。
30万円(税抜)のパーティーなら、15,000円分のポイントが一気に貯まり、幹事様の打上げや次回開催時の費用替わりにご使用いただけます。
パーティーの当日の入会でもポイントが貯まるので安心です。